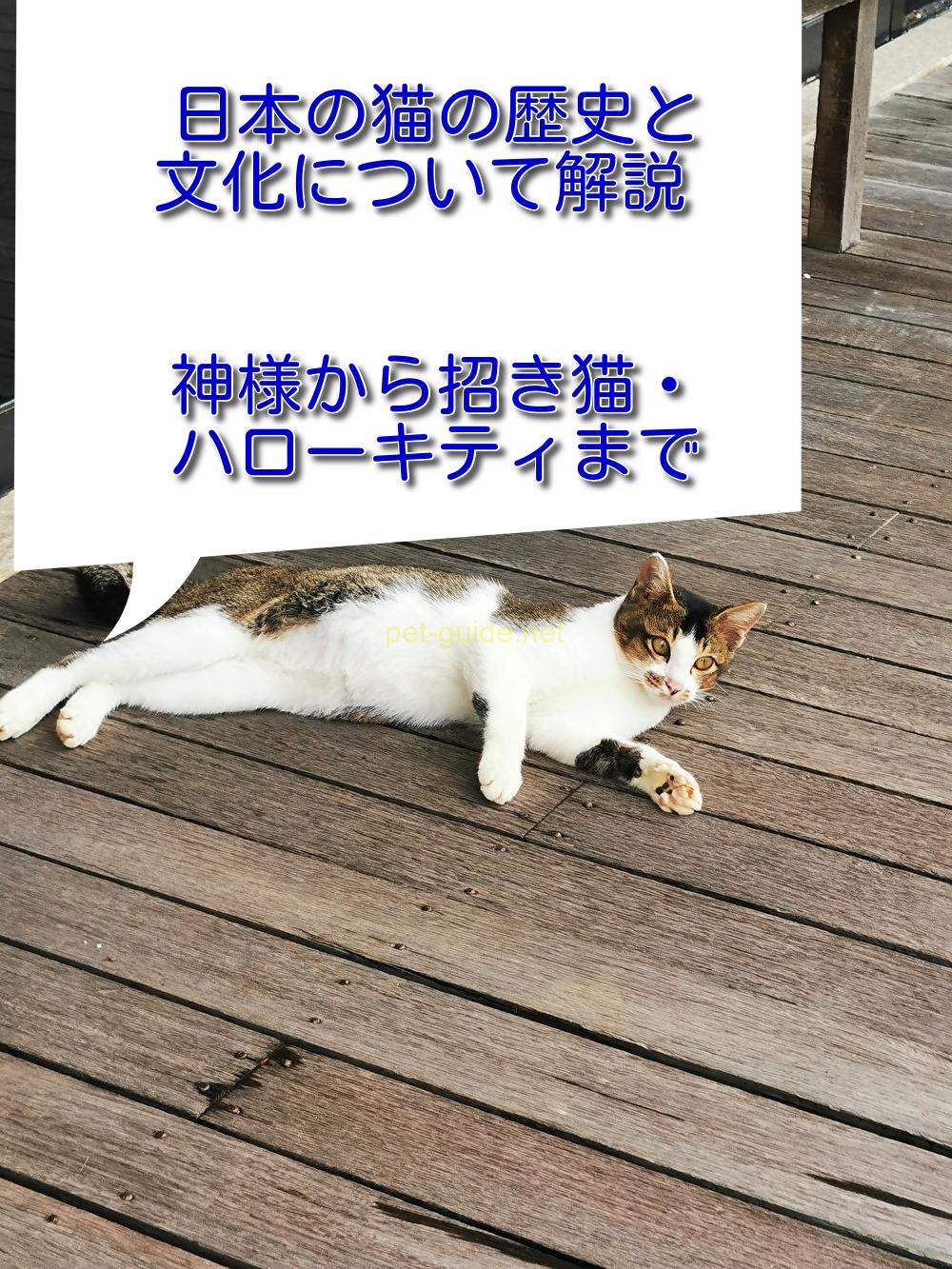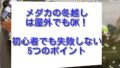導入
日本人にとって猫は、ただのペットではありません。
長い歴史の中で「守り神」として敬われたり、「幸運の象徴」として親しまれたりしてきました。
時代ごとにその役割は大きく変わり、今では癒しやSNSの人気者として生活に溶け込んでいます。
今回は、平安時代から現代まで、日本における猫の文化と人々との関わりをたどってみましょう。

平安時代近辺|貴族に愛された高貴な猫
日本に猫が伝わったのは奈良〜平安時代とされています。
仏教の経典や大切な文書をネズミから守るために、中国から船に乗せて連れてこられたのが始まりでした。
当時の猫は非常に希少で、庶民の目に触れることはほとんどありませんでした。
宮中や貴族の邸宅で可愛がられ、その姿は日記や絵巻物にも描かれています。
例えば『源氏物語』や『枕草子』にも猫が登場し、遊ぶ様子や美しい毛並みが記録されています。
こうして猫は「高貴な動物」として特別な存在となり、愛玩動物としての地位を確立していきました。
江戸時代〜戦前|庶民の守り神から文学の主人公へ

守り神としての役割
鎌倉・室町を経て江戸時代に入ると、猫は一気に庶民の生活に浸透します。
農村では穀物を守る「ネズミ退治の達人」として頼りにされ、漁村では「海を無事に渡る守り神」として船に同乗させる風習が広がりました。
猫の瞳が暗闇で光ることから「夜を見通す力がある」と信じられ、魔除けとしても重宝されました。
招き猫と庶民文化
江戸時代には、今も私たちが親しむ「招き猫」が誕生します。
商売繁盛や金運を呼ぶ縁起物として、店先に置かれるようになった招き猫は、町人文化の象徴とも言える存在です。
浮世絵や戯画にも猫が登場し、「かわいらしい動物」として庶民に親しまれました。
文学に登場する猫
明治期に入ると、猫は文学作品にも登場します。
夏目漱石の『吾輩は猫である』はその代表で、猫の視点を通して人間社会を皮肉る作品は大きな反響を呼びました。
この頃から「日本人は猫好き」というイメージが確立し、文化的なシンボルとしての猫が強調されるようになります。
戦後〜近代|癒しとポップカルチャーの象徴へ

家族の一員としての猫
戦後の日本では、都市化の進展に伴い猫はさらに身近な存在となりました。
室内で飼われることが増え、「家族の一員」としての地位を得ていきます。
観光・ビジネスへの広がり
現代ではSNSや動画投稿サイトを通じて、日本の猫の可愛い仕草やユニークな行動が世界的に注目されるようになりました。
「猫カフェ」や「猫島」といった観光資源も人気を集め、猫文化は地域活性化にも貢献しています。
アニメ・キャラクター文化に生きる猫
アニメやキャラクター文化の中でも、猫は大活躍しています。
『ドラえもん』や『ジジ』(魔女の宅急便)といった人気キャラクターは、猫をモチーフにした存在として幅広い世代に愛されています。
さらに、世界的に有名な『ハローキティ』は日本発のキャラクターとして国境を越え、猫文化を国際的に広める象徴ともなりました。
まとめ
猫は、平安時代には貴族に愛された高貴な存在として、江戸時代には庶民の守り神や招き猫として、そして戦後から現代にかけては癒しと文化の象徴として、人々の生活に深く結びついてきました。
古代から続く「幸運を呼ぶ存在」という信仰は今も変わらず、猫は私たちの暮らしを豊かにする存在であり続けています。
猫の歴史をたどることは、日本文化の奥深さを知ることでもあり、同時に日本人がいかに猫を大切にしてきたかを再認識することにもつながります。